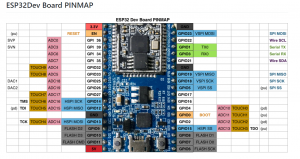ここまでで見えたこと
ESP32をターミナルから扱うとWIFIをSSCコマンドで操作できる。
例題をやったら携帯のWIFIスキャンに引っかからなくなった(^_^;
コマンドはここにある。何やらRTOSとかあるな。いいね!
ファームの取り扱い
最初のファームを吸い出しておくことが必要。まあ戻す必要がなければ不要だと思うけど。結構ここで引っかかってる。それと関連することが周りを取り込み始めた。マイコンで開発するそのものになってきた。やはりラズベリーパイとは違うね。ラズパイは秀逸だ。ラズパイZeroという選択肢もありだ。
しかし、簡単でないからいい。小生の仕事だったことが丸々活きるからね。
●esp32tool
Windowsd10のesptools.exeで行う場合とWindows10に入れたpythonでやる方法があるらしい。調査中。Pythonのツールは以下で導入できた。
$ pip install esptool
引用:いくつかのPythonのインストールでは、これはうまくいかず、エラーがpython -m pip install esptoolうpython -m pip install esptoolまたはpip2 install esptool試してみてください。インストール後、デフォルトのPython実行可能ファイルディレクトリにesptool.pyインストールし、 esptool.pyコマンドで実行する必要があります。
最初のプログラム
●スケッチ
さて、いよいよスケッチでプログラムを実行させることに。あちこち読んでいくとそれなりの簡易ツールなようだ。例題が使えるなど複雑なことをやらせなければ便利に使えるようだ。
本格的にならメーカー専用の開発ツールを使用とある。さっと見ただけだが、おいらの昔のツール使いという感じだな。まあAuduino自体が専門家でなくてもマイコンが扱えるということに特化してるようでc++のクラスとしての実装だろうか、うまくまとまったライブラリを持っている。スケッチはcだろと思ってたが、c++のご利益かと関心!
以下はスケッチのESP32のサンプルコード。
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
Serial.println("Hello World.");
delay(10000);
}※ESP32のファームウェアは、ArduinoIDEで開発をすると上書きされてしまうので、ArduinoIDEで開発を行ったあとにATコマンドモードに戻したくなった場合、別の手順を踏む必要があります。
●MicroPython
このところ会社でちょっとしたプロトタイプをPythonで頑張っている。仕事がらGPIBとかSerial(RS232C)。
ESP32とは違うけどIoTはラズパイも当然視野に入っていて、こちらでもI2Cで冶具をc#でプログラムする前ににプロトタイプ用で使用している。ということでESP32もPython環境にしたい。
スケッチでプログラムはこのままでいいらしいが、Pythonでとなるとファームを書き換える必要があるらしい。スケッチ用というか最初のファームを吸い出して後で戻せるようにするとかあるな・・・。